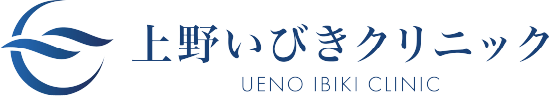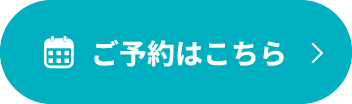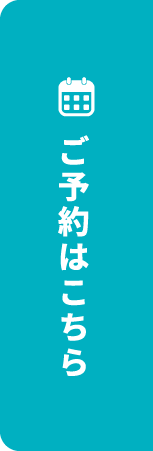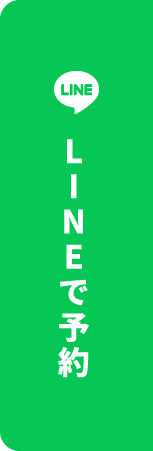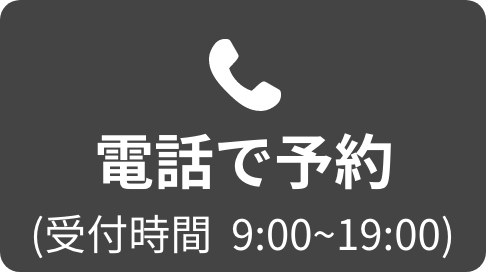「睡眠障害」診療科名に追加を検討 日本人はOECD最下位の睡眠不足 厚労省が議論開始

医療機関が掲げることのできる診療科名に「睡眠障害」を加えるかの検討が厚生労働省の専門部会で始まった。日本人の睡眠時間は経済協力開発機構(OECD)加盟国中最下位で、睡眠の悩みを抱える人は相当数存在するとみられるが、適切な診療にたどりつけていない〝睡眠障害難民〟の存在も指摘される。診療科名への追加が実現すれば、受診先を探しやすくなり、早期の治療が期待できる。厚労省は、来年3月ごろまでに議論を取りまとめる方針
との報道がありました。(産経新聞)
確かにこの睡眠障害ですが、様々な理由が考えられます。
精神依存や薬物依存、脳神経疾患など根本治療が必要なものも多くあります。
しかし実際多いと思われるのはやはり、いびきと睡眠時無呼吸が最も多いと考えらます。
この記事の目次
睡眠障害と睡眠時無呼吸の関係
睡眠時無呼吸では、睡眠中に何度も呼吸が止まったり(無呼吸)、途切れ途切れに弱くなったり(低呼吸)します。
そのたびに体は低酸素状態に陥り、脳は呼吸を再開させるために断続的に覚醒を繰り返します。
これにより、ぐっすり眠ったつもりでも実際には**数十回、時には数百回もの「中途覚醒」**が起こり、睡眠の質は著しく低下します。翌朝の強烈なだるさ、日中の耐え難い眠気、集中力がなくなる。
こうした症状は単なる寝不足ではなく、慢性的な低酸素と睡眠分断による身体の悲鳴です。
なぜ「気づきにくい」のか——“入眠はできている”という落とし穴
これは実際本人が気づくことも少なく報道のような睡眠障害であると自分では判断できないことが非常に多いです。理由は入眠できないわけではく、良い睡眠を得られていないという意味です。
つまり寝ているのに疲れが取れないというのは実際に寝ていないという睡眠障害に等しいのです。
そして報道のようにどの科を受診してよいのか判断に迷うことが考えられますが、そもそもこの睡眠時無呼吸症候群を患っているにも関わらず、本人に睡眠障害の自覚がないため、標榜科を新設したとしても無呼吸による睡眠障害を認識して受診することは非常難しいのではないかと考えられます。
典型的なサインと“自覚なき”日常の支障
-
いびきが大きい/一定しない(途中で止まり、再開時に「ガッ」と音がする)
-
熟睡感の欠如(長時間眠っても回復しない)
-
午前中の頭痛・口渇(口呼吸・低酸素の影響)
-
日中の強烈な眠気(会議・運転・デスクワーク中の舟を漕ぐ)
-
集中力・判断力の低下/作業効率の悪化
-
高血圧の指摘、メタボ傾向(SASと関連しやすい)
当人よりも家族や同室者が先に気づくことが多いのも特徴です。「いびきが止まって苦しそうだった」「寝返りが多い」「朝から機嫌が悪い」などの他者観察は貴重な手掛かりになります。
健康リスクは“寝不足”の一言では片づけられない
睡眠時無呼吸は単なる生活の質(QOL)の問題にとどまりません。
夜間低酸素と睡眠分断は交感神経を持続的に刺激し、次のようなリスクを高めます。
-
高血圧・不整脈・心不全・脳卒中・心筋梗塞のリスク上昇
-
糖代謝異常・2型糖尿病の悪化
-
交通・労災事故の増加(居眠り運転等)
-
抑うつ・不安症状の併発
-
**勃起機能不全(ED)**など循環・ホルモンバランスの乱れ
つまり、「朝だるい」=体が悲鳴を上げているサインと捉えるべきで、早期に疑いを持ち、適切に評価することが重要です。
受診先に迷うのは当然——“標榜科”よりも「評価体制」が要
「何科に行けばいいのか分からない」という声はよく聞かれます。実際、SASは耳鼻咽喉科、呼吸器内科、循環器内科、睡眠医学専門外来など、複数領域にまたがる疾患です。
重要なのは**“どの科か”よりも**、**SASの評価と治療の流れ(診断→重症度判定→最適治療の選択)**を一貫して提供できる体制があるかどうか。標榜科を新設しても、当の本人に自覚がなければ受診につながりにくい——まさにここがSASの本質的なハードルです。
他人のいびきがうるさくて眠れない——“受動的いびき被害”が生む睡眠障害
同室の家族やパートナー、ドミトリー・寮・社宅・病室・深夜の移動手段など、自分は健康でも「他人のいびき」で眠れない状況は珍しくありません。これは単なる騒音問題ではなく、繰り返される入眠遅延・中途覚醒・早朝覚醒によって、やがて入眠への不安(条件付け)→慢性不眠へ移行し得る“受動的いびき被害”です。以下では、メカニズムと対策をまとめます。
なぜ「いびき」は眠りを壊すのか
いびきは断続的で予測不能、かつ音量・音程・間隔が揺れるのが特徴です。人の脳は一定の環境音には慣れますが、変動ノイズは脅威と判断しやすく、**覚醒反応(マイクロアラウザル)**を誘発します。
結果として、
-
入眠に時間がかかる
-
眠りが浅く、微小覚醒の積み重ねで熟睡感が消える
-
翌日の眠気・倦怠・集中力低下が持続
といった実害が生じます。これが続くと「また眠れないのでは」という予期不安が強化され、音が無くても眠れない条件性不眠に陥ることもあります。
関係性を壊さずに“音源”へアプローチ
「ここ数日、夜中に何度も起きてしまって仕事に影響が出てる。お互いに良い睡眠を取りたいから、一緒に対策を考えてもいい?」などマイルドに言うのがよいでしょう
頭ごなしに「あなたのいびきがうるさくて眠れない!別の部屋で寝てくれ!」とストレートに言ってしまうと言われた本人は悪気も迷惑をかけている気も全くないため、「いびきぐらいで騒ぐな」対抗心が芽生えます。
このようにいびきは他人までも睡眠障害に陥れてしまう恐ろしい疾患なのです。